
電話を切ってしばらく経つのに、姉の紗枝の声が耳にしぶとい。
東京で働く佳織を、紗枝がよく思っていないことは、かねてより感じるところだった。妹をそのように思う紗枝が、佳織は疎ましかった。そんなときは、いっそ哀れみを抱いて気持ちを整理するのだった。
姉はいまだに母と一体なのだ。可哀想な人だ。母の代わりに怒っているつもりなのだろうか。
「子供の頃、いちばん怒られたのってどんなときだった?」
佳織はふと森に尋ねた。外で強い風が吹く音が聞こえる。森がしばらく無言だったので、「寝ちゃった?」と質問を重ねる。
「いや、起きてるよ。…考えてみれば、俺怒られたことないなあって。改めて思うと変なんだよ。警察の世話になった直後ですら、親父は、魚の釣り方とか、焚き火のつけ方とかそんな話しかしないし、学校の先生は『こいつは仕方ない』みたいに諦めてる感じだし」
森の肩口に預けていた頬を起こして、佳織は彼の表情を見た。天井をまっすぐ見上げているのが、夜目(よめ)にもわかった。森の目は凪いだ海のように穏やかだった。穏やかすぎて、いまにも消えそうな気がした。少し怖かった。
「怒ってほしかったの?」
「フフッ」森はほのかに笑った。「怒ってほしい、か。その可愛げがあればよかったのかもね」
森の視線の先に、森の母が見えているように思えた。佳織は、会ったこともない、これから会えるとも思えない、森の母の顔を想像した。目元の涼しい美人だった。森が最後に母を見たとき、彼女はどんな表情を浮かべていたのだろう。
「大切な人を守るための行動を」
この数ヶ月、よく耳にする言葉だ。佳織はこれを聞くたびに、ぼんやりとした違和感を覚えていたのだった。いま、森の目を見て気づいたことがあった。
情に訴えるウィルス対策って、なんか変だ。遠くの親に感染させないのも情なら、森がそうしたように、名も知らぬ若者を助けるのも情だろう。大切な人は家族だけなのだろうか。情に優先順位があるのだとしたら、それは果たして情なのか。
森の母を想像しているはずが、いつしか自分の親を思い出していた。佳織は、なぜか少し悔しい気持ちになる。
明日電話しよう。自らそう思うなんて、随分久しぶりのことだ。
朝を迎えたとき、そこにまだ男がいるのを苦手だという女は少なくない。男の方もそれは承知しているが、夜明けを待たずに姿を消すのも悲しい。だから朝の男は、なるべく言葉少なに振る舞うのだ。
佳織が男との朝をどう感じるタイプなのか、森はまだ知らない。今後、そんなあれこれを少しずつ知っていくことになるのだろうか。そう思う森の心はどこか晴れない。女のことを知れば知るほど、女といられなくなるのはなぜだろう。知ることと愛することが、どうして一致してくれないのだろう。でも、そんな俺の厄介加減に、女は気づかないはずだ。俺は女の前では陽気だから。
さっきから、佳織が、ではなく、女が、と考えていることに気づき、森は自分を忌々しく思う。
窓の外は、もうすっかり明るい。カーテンの隙間から覗く、とりとめのない景色を見るともなく眺めた。一軒家が立ち並んでいる。どれも古い。何十年も前からそこにあるように思えた。その隙間を縫って、ところどころ緑が目に入る。庭ではない。畑のようだ。ここも東京。まるで知らない街のようだった。空が広い。犬の鳴く声がどこからか聞こえる。

森が生まれ育った東京は、ネオンとパトカー、嬌声に怒号の街だ。人間がほんのひととき黙っても、それを待っていたかのようにカラスが喚き散らす。
森がいま住まう東京は、ビルがびっしりと立ち並んでいるのに、音もしなければ色も付いていない。海までそう遠くないが、海は見えない。
森が仕事場にする東京では、見回せば必ずどこかで重機が動いている。駅前など、数十年もの間、1日も工事が止まったことがないとさえいう。とにかく転がり続ける街。行き先はわからない。
東京で感染者急増。東京の夜の街に注意。東京との行き来に警戒を呼びかけ。ニュースが連日叫ぶ。どれも東京で起こっている本当の出来事なのだろう。
東京、東京、東京…。東京というのは一体どこのことなのかと、森は思う。
「おはよう。早いね」
目を覚ました佳織が言う。起き抜けのせいか、普段より声が低い。
「うん。コーヒー屋は早起きじゃないとね」
「もう出かけるの?」
「そうだね」
「ちょっとだけ待って」
佳織が窓際に立つ森の元に駆け寄る。森の首元に佳織の顔が押し当てられる。
朝の女の匂いがした。幸せな匂いだった。森は、幸せの種をまたひとつ使ってしまった気がして、胸が痛んだ。
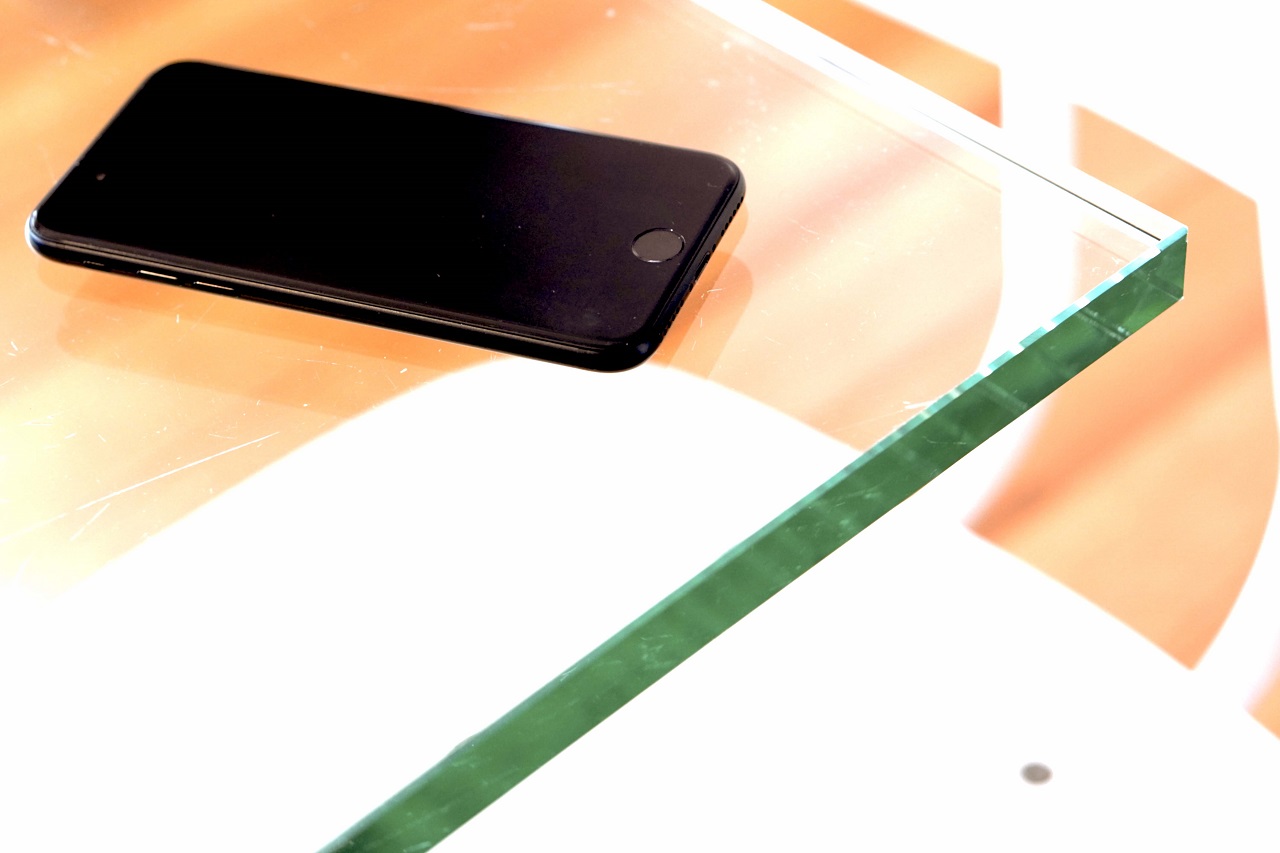
森が出かけた後、佳織は再びベッドに入った。1時間寝てから、実家に電話をした。夜だと話が長くなりそうなので、朝を選んだ。
電話には父が出た。少し驚いた。定年後も5年間嘱託で会社に残った佳織の父だったが、それも昨年で終わったので、家にいること自体に不思議はない。しかしまだ慣れない。
左肩から腕にかけて、少し痺れるのだと、父は言った。学生時代、ラグビーに励んでいた頃に頚椎を痛めて以来の古傷だ。騙し騙し患部と付き合ってきた父だったが、佳織が小学生だった頃、とうとう首にメスを入れた。部位が部位だけに、佳織も姉も心配でたまらなかった。それから20数年順調だと聞いていた。手術前後の不安な記憶がよみがえる。
「筋トレに行けないからな。ジムは再開しているのに、母さんも紗枝も許してくれない。それが問題だ」
しかし当の父は、のんきにそんなことを言っている。声もいたって元気そうだ。
「筋トレって、そんな無理していいの?」
「筋肉が落ちてきたから痺れるんだ」
「それ自己診断でしょ」
「自分の体は自分がいちばんわかる」
佳織はため息をつく。
「そういうのやめてくれない。聞いてて不安になる」
「お、すまんすまん」
ほどほどに慕われ、ほどほどに疎まれ、ほどほどに心配される。父はそんな存在だった。佳織は、この人のことをどれくらい知っているのだろうと、ふと思った。もしかしてなにも知らないのではないか。
「お姉ちゃんからは、帰るなって言われたんだけど、帰ったらダメかな?」
ついそんなことを口に出していた。
「娘が帰ってくるのをダメとは言わない。でも父さんのことなら心配いらない」
父は穏やかにそう言ってから、「母さんに代わる」と告げた。佳織は思わず緊張する。しばらくの空白の後、
「もしもし。あなたは大丈夫?変わりない?満員電車乗ってない?会社、窓開いてる?」と、母は矢継ぎ早に質問した。
有無を言わせないところは相変わらずだったが、姉のような嫌味は感じなかった。それだけで佳織はほっとしている。
「うん。大丈夫。在宅勤務も多いし。お姉ちゃんからマスクいっぱいもらってるし」安心材料だけ伝えた。
「うん、そう、うん」と母はひとりで納得したように相槌を続けた。その様子に佳織は却って不安になる。
「お父さん、大丈夫なの?」
「え、ああ、そうなのよ。大丈夫じゃないのよ」
母は声をひそめる。
「大丈夫じゃないの?」
佳織は逆に声が大きくなる。
「ううん、元気にはしてるわよ」
なんとなく要領を得ない。
「手術はしないの?」
「難しいところなのよね。どちらがいいのか。万が一うまくいかなかった場合を考えるとね。お父さんも私も高齢になってきたから」
佳織は驚いていた。母の口から高齢などという言葉が出たからだ。母は、娘たちをいつも実年齢より子供扱いした。生理が来たときも、それを嫌がった。目を背けたようにさえ見えた。いきおい、母自身もどこか大人になりきれていないようなところがあった。それが、高齢だなんて。
「お医者さんとよく相談してね。でもいまの時期病院行くの怖いのかな?そっちの状況よくわからないけど。お姉ちゃんの意見も聞いて」
アドバイスになっているのかなっていないのか、佳織自身わからないまま、通話を終えた。襲いくる無力感を、部屋に漂う森の余韻で中和したかったが、そう簡単ではない。
広い世界を見ることこそ正しい選択だと思って、佳織は東京に出た。そしていまもそのつもりで東京にいる。地元に残る人生は考えもしなかったし、後悔もない。
姉がウェディングドレス姿を親に見せたとき、直感的にこれは私のやることではないと思った。しかしそれは姉という木の陰に隠れただけだったのか。親の老い。できれば考えたくない。私は都合のいいときだけ、姉の木陰で涼んでいるのか。佳織は初めてそんなふうに感じた。

いつの間にか、夕日が見える時間だった。夕焼けの上を、雲が覆っていた。
今日はリモート会議が2件あった。大勢の人に会ったような、誰とも会っていないような、不思議な感覚に佳織は見舞われる。眠る前に誰かの顔が見たいな、と思う。
森がいいけど、連日会おうと言うと、男は大抵しおれる。ひかるを誘って「つるつるの湯」に行ってみようか。
佳織が考えていると、誰かからのテキストメッセージを報せる軽い音が聞こえた。森からだった。胸が高鳴る。
しかし文面に目を落とした瞬間、その高鳴りは消え去り、佳織は戸惑う。用件は短かった。
「火曜、道玄坂『L』12時。先月と同じ場所」
これは、私に宛てたものではないとすぐに分かる。送り間違い。誰しもミスはある。すぐ森に教えなければ。
少なくとも先月、森は誰かに会った。そして今月も会おうとしている。仕事の話かもしれない。ならば尚更誤りを伝えてやらなければいけない。
そう思うのに、何かがそれを拒む。
窓の外の雲がいよいよ黒く、そして厚い。
文/大澤慎吾 撮影/手塚旬子









