中目黒駅につく手前で、お父さんに肩を揺すられて起きた。
いつの間にか眠ったみたいだ。丸山くんの家からの帰りだったことを思い出し、がっかりした。
私が電車で寝てしまうと、お父さんはいつも「仕方ない。抱っこしてやるよ」とつまらない冗談を言うけど、この日はそれもなかった。
自分の部屋でベッドにうつ伏せになり、お母さんが二度と帰ってこないことについて想像した。もしそんなことになったら、私はもう立てそうにない。それなのに想像をやめられなかった。
いっそ本当に帰ってこなくなり、お母さんも、お父さんも、私の心も体も何もかもムチャクチャになればいいとさえ思った。
たとえ話ではなく、胸が実際に痛んだ。でも100のうち1くらいだけ、その痛さを気持ちよく感じていることに私は気づいていた。
お母さんは、私たちより3時間遅れて帰ってきた。いつもなら私はもう寝ている時間だ。
玄関の鍵が回るガチャガチャという音に、私の体は固くなった。走ったあとみたいに心臓がドキドキした。嬉しくないわけではない。ほっとして涙があふれそうなほどだった。それなのに、ベッドから起きて出迎える気にはなれなかった。
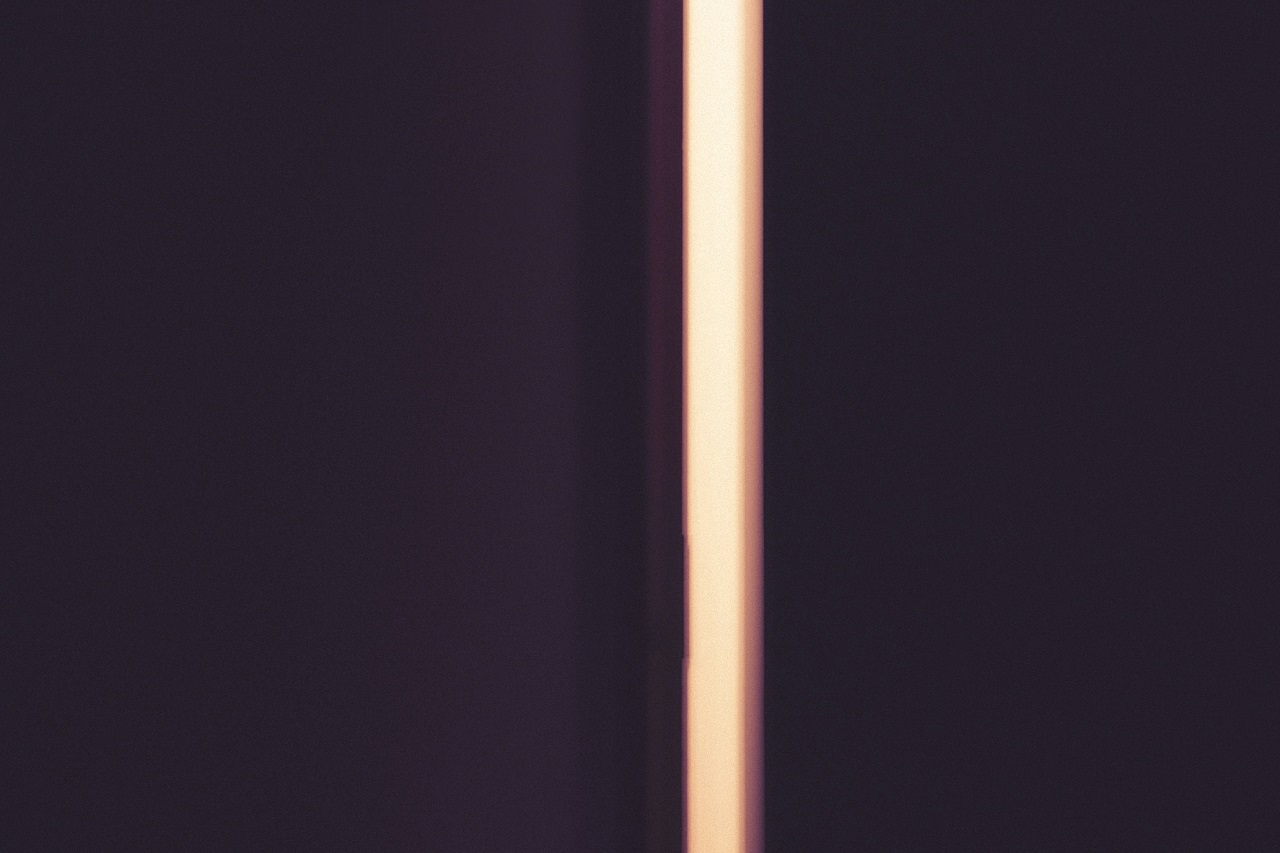
お父さんとお母さんは、小さな声で話していた。ドア越しの声はゴニョゴニョして何を言っているかはっきりとはわからなかった。聞きたくなかったので、ちょうどよかった。
しばらくして、やっとウトウトしたところで誰かが部屋のドアをそっと開けた。明かりが細く差し込んだ。私は眠っているふりをした。
うっすらとお母さんの香水の匂いがした。いつもの匂い。私はそれが好きだったはずなのに、むせそうになった。
お母さんは息をしていないみたいに静かだった。
もう一度ドアが開き、お母さんが部屋から出たあとも、甘い匂いがいつまでも私の鼻に残っていて、落ち着かなかった。
「二分の一成人式」が近づいてきた。
こんな時にお父さんお母さんへの手紙を書かなきゃいけないなんて、私は運が悪い。
お父さんは最近口数が少ない。私が学校から帰ってきても「元気かな?」と聞かなくなった。夕ご飯も手抜きみたいなメニューが増えてきた。今まではミートソースも一から手作りだったのに、ところどころ缶詰を使ったりしているみたいだ。味が変わった。
ランニングは毎日しているらしい。元気がなくても走れるのは不思議なことだ。
お母さんも変わった。明るかった髪の色が少し地味になった。服の色も黒やこげ茶が増えてきた。冬を意識したファッションなだけかもしれないけれど、どことなく元気がない気がする。
鹿児島先生は、正直に思ったことを書けばいいと言う。でも正直ってなかなか大変だ。誰だって言えないことはあるだろう。
でもがんばって正直に言えば、今回はお母さんが悪いような気がする。私の前ではあの話はなかったことになっているから、結局詳しいことはわからない。でもそんな気がする。
だからと言って、お父さんの味方をするのもなんだか気が進まない。お父さんには悪いけど。
私はランドセルから便箋を取り出して、机の上に広げた。女子も男子も同じ水色の便箋を渡された。何人かの女の子は、ピンクがよかったなあとヒソヒソ話していた。
鉛筆を手にとって、思い切って書き始めた。
「お父さんへ。
私はお父さんには、普通のお父さんになってほしいと思っています。
普通に朝早く家を出て、普通に会社で仕事をして、普通に夜遅く帰ってきてほしいです。そうすればお母さんと仲良くできると思います。
10年間育ててくれてありがとう。」
正直に書いたらひどいことになった。人前で読めるわけがない。私は消しゴムで丁寧に消した。
もう、なんなのこの行事。いったい誰が喜ぶのだろう。

いつもは休みの土曜日、特別に学校があった。「学校公開」といって、丸一日が参観日みたいになる。たくさんの大人たちが学校に詰めかける。
「二分の一成人式」は5,6時間目を使って行われることになっていた。
みんな口では「やだなー」とか言っているのに、テンションが高かった。休み時間の教室はいつもの倍、騒がしかった。
そんな中、佳音ちゃんは窓の外を見たりして静かだった。トイプードルのボンが死んでしまった落ち込みからは、だいぶ立ち直ったようだけど、あれから少し大人っぽくなった気がする。今日も濃い紺色のワンピースを着ている。
私はとにかく憂鬱だ。大好きな緑のカーディガンを着てきたけど、気分は晴れない。
5時間目のチャイムが鳴り、体育館にゾロゾロと移動した。親たちがすでに着席していた。なんとなく仲良しグループで固まっている感じだった。そういうのって大人になっても意外と変わらないみたいだ。
そんな時、私のお母さんは輪に加わらない。別に気取っているわけじゃないと思うけど、なんか浮いている。
お父さんはもちろん浮いている。ふたりは端っこに並んで座っていた。

階段みたいになったステージに整列して、礼をした。
代表委員のあいさつのあとは、全員での合唱だ。
私たちの学年は全部で34人。もちろん1クラスしかない。
お父さんはいつも「田舎の分校みたいだな」と笑う。私は分校がどんなものか知らない。お父さんだって東京生まれだから、本当は知らないはずだ。
私は合唱がそんなに好きではない。そもそも歌うことが苦手だ。
でも、ここまでは何度も予行演習をした通りなので、気が進まないなりになんとか乗り越えた。
その後は、いよいよ手紙を読み上げる時間だ。
トップバッターはクラス委員の萌ちゃんだった。
萌ちゃんは「お父さんお母さん、いつも…」と読んだだけでいきなり泣いた。私はびっくりした。そこまで本気のイベントだとは思っていなかった。みんなも驚いたみたいで、空気がピリッとした。
その後は、将来の夢とか親への感謝とか、みんな真剣なトーンで頑張って読んでいた。
ステージの上からは、親たちの顔がずっと見えている。誰もがお面みたいな笑顔で聞いていた。あまり見ないようにしていたけど、私のお父さんとお母さんも変に優しい笑顔だった。
私の順番が近づいてくる。心臓がドキドキする。親の笑顔が怖い。
隣の子が読み終えた。私は立ち上がり、手紙を広げる。
「お父さん、お母さん。10年間、育ててくれてありがとう。お母さんは仕事を頑張っていて、私たちの暮らしを支えてくれています。お父さんの作るご飯はおいしいです。そんなふたりと一緒にいられて毎日幸せです」
途中から読んでいて恥ずかしくなってしまった。本当のことだけど、なんでこんなことを人前で言わなければならないのか。
「私の将来の夢はまだ決まっていません。でも、自分が幸せだと思う生き方をしたいです」
自分の番が終わったというのに、体の震えが追いかけてきた。居心地が悪かった。でも本当に嫌だったのは、式が一通り終わって自由時間になってからだった。
普段あまり話したことのない友達のママたちが、口々に「詩子ちゃんの手紙よかったよ」「いいわねえ詩子ちゃん」「羨ましいわ」などと言いながら寄ってきたのだ。不気味だった。何を言っているのだろうこの人たちは、と思った。私がそんなふうに褒められているのに気づいたのか、お父さんはスタスタと体育館から出て行った。
帰りの会が終わって下校の時間になった。お母さんがひとり、校門の前で待っていてくれた。嬉しかった。でもそれ以上に気まずかった。一緒に歩きかけたけど、勝手に口が動いて「友達と約束したから、お母さん先に帰ってて」と言ってしまった。
お母さんのきれいな眉毛が、少しさびしそうに動いた。「そう。わかった」とだけ言って、お母さんは帰って行った。
お母さんの背中が見えなくなると、学校の近くにある公園に入った。ベンチが空いていたので、ランドセルを背負ったまま座った。友達との約束なんて、ない。
いつもは小さな子どもたちがたくさん遊んでいるのに、今日は誰もいない。目の前の芝生広場にロープが張られ、立入禁止になっているからだ。芝生を育てるためらしい。誰も入れない広場をぼんやり見ていた。本当は何も見ていなかった。
私はどんな大人になりたいのだろう。ふとそんなことを思った。しばらく考えたけど、全然わからなかった。
強い風が一回だけ吹いて、私の髪を揺らした。すごく冷たい風だった。でもなんだか気持ちよかった。もう一回その風に吹かれたくて、私はベンチに長く座った。
だんだん太陽が弱くなって、代わりに夜の匂いがしてきた。夜の匂いは少し怖い。風はまだ吹かない。私はどんな大人になりたいのだろう?
文/大澤慎吾 撮影/塚田亮平









