
決して急がず、それでいて間延びせず、絶妙の間合いで私たちの前に寿司が置かれる。先生はそれをすかさず口に運ぶ。私も真似をしてどんどん食べる。舌から脳へ、快感のようなものがわき起こるから驚いた。
「鮨しおみ」という名のこの店は、昼も夜も“おまかせ”なので、何がどれだけ出てくるのか、初心者の私にはよくわからない。
いつだったか、父から「寿司はあっさりしたものを先に、味の濃いものを後に」と教えられたかすかな記憶がある。
それを信じれば、穴子が出てきたということは終わりが近いのだろうか、などとやや論理的に考えてみる。本当はまだ食べていたい。
「鴨下さん、お腹の具合はいかがですか?追加があれば頼みましょう」
鳴滝先生が私に尋ねた。やはりそろそろ終わりらしい。
「はい。お腹はもう、すっかり満足しています」
嘘をついた。
それより気になったのは「鴨下」という名字に主人が反応したように見えたことだ。
一瞬手を止めて、私の顔をちらっと見た。目が合った。ほんの半秒間ほどの間に主人は何かを察したようだった。
目の前にいるのは、母の昔の恋人かもしれないのだ。
肝心なところを私はつかんでいない。鳴滝先生は露骨な詮索などの無粋な真似は、もちろんしない。
私たちの隣の席の男性が会計を頼んだ。常連のような雰囲気だ。お店を手伝う女性が丁寧にお釣りを渡している。すると、その常連さんが
「奥さん、来週金曜の晩、予約できるかな」と女性に声をかけた。確かに聞いた。奥さん、と言った。とりあえず、これは、吉なのか。
常連さんが帰ると、カウンターには私たちだけになった。お昼の営業はそろそろ終わるのだろう。
「ごちそうさまでした。美味しかったです」
先生が、主人に礼の言葉を伝えた。
「どうもありがとうございます」
と、主人が応じる。
胃袋の満足感とは裏腹に、胸のつかえが取れないまま、引き戸を開けて外に出た。
現場の証拠というわけでもないが、店の外観を写真に収めた。
ついでに母のインスタを開いてみた。
投稿が増えていた。川の写真。遠くに橋が見える。金沢市内には大きな川が2本流れていると今回知った。2本のうちのどちらかだろう。
「川の流れが変わることはありません。それに逆らうか従うかは自分で決めること」
また不穏かつ思わせ振りなことが書いてある。
しかも誰かがコメントを寄せていた。そのアカウントに私の目は釘付けになった。takuro_kamoshita 父だった。
「塩見君のお兄さんには会えたのですか」
小細工も何もない。素性を隠してコメントしている私は立場がない。
「塩見君」というのは、この「鮨しおみ」の主人のことだろう。兄が事故に遭ったので弟の自分が跡を継いだと言っていた。そのお兄さんに、母が会う?
黒塀の前で動けずにいる私を急かすこともなく、鳴滝先生は宙を見ていた。
すると内から戸が開き、主人が出てきたので、思わず体が硬くなった。
割烹着の上に、パタゴニアの黒いダウンジャケットを羽織っている。
どこかに用があるのかと思いきや、私たちの前で足を止めた。
「先ほどはありがとうございました。失礼ですが、鴨下さんとおっしゃるのですか?」
主人が私に聞いた。私は先生の顔を横目でちらりと見た。先生はいつもの穏やかな表情だ。
「はい。そうですが…」
恐る恐る答えた。
「鴨下拓郎さんの、お嬢さんですか?」
やはり父の名前を知っていた。
「はい。そうですが…」
全く同じセリフを口走る。
主人はひとつ息を吐くと、
「お母さんにお伝え願えませんか。金沢にはもう来ないでほしいと」
そう言った。
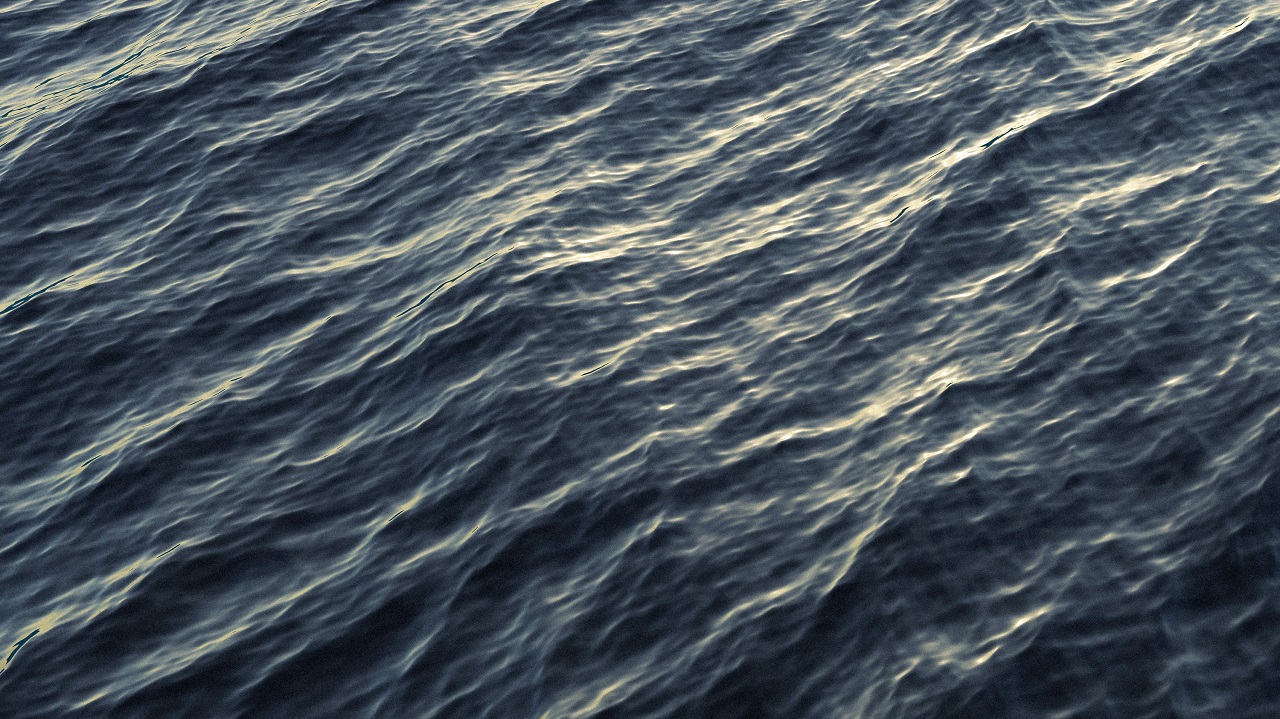
頭が痛む。先生と並んで歩いている。当てはない。
道幅が広い。これが加賀百万石というものなのか。
街路樹には雪の重みで折れないように「雪吊り」が施されていた。雪だけがまだだった。
橋に差し掛かったところで歩くのを止め、川を見た。浅野川というらしい。母のあげていた写真に似ている。
黒塀の前で「鮨しおみ」の主人に聞かされた話が頭を巡っている。でもぼんやりしてしまって、核心にたどり着くことができない。
私の両親と塩見さんは、大学の同級生だった。テニスサークルで知り合い、仲がよかったらしい。父と塩見さんにとって、母は気になる存在だったが、友情を優先して、お互い行動には打って出なかった。
夏休みに入り、塩見さんは金沢への帰省に同行しないかと、父と母を誘った。そこで、寿司の修業中だった塩見兄に出会う。
塩見兄はひと目で母に心を奪われた。母もその後度々金沢を訪れていたようだから、憎からず思っていたのだろう。しかし態度をはっきりさせなかった。
そして進展がないまま1年が経った頃、母への思いを募らせた塩見兄は奇行に走る。ある夜、ひとりで金沢城に忍び込み、高さ20メートルはあろうかという石垣のてっぺんを目をつぶったまま歩いたのだった。
石垣の上を目をつぶって歩くことと、恋慕の情とがどうつながるのか、私にはさっぱりわからないが、鳴滝先生によると「大いにあり得ます。特に若いうちは」とのことなので、そうなのだろう。
結果、塩見兄は石垣から転落、命は取り留めたものの、全身打撲、全身骨折、そして精神的ダメージにより、寿司屋の道を自ら閉ざした。そして弟の塩見さんが金沢に呼び戻された。
その後、どういうつもりか、父と母は交際を始めるのである。
「お母さんを責めるつもりはありません。私の兄が馬鹿をやっただけですから。でも、私が鴨下さんのご家族に寿司を出すのは、これを最後にさせてください。もちろん兄の居場所もお伝えしません」
塩見さんは頭を下げた。言葉も態度も終始丁寧だったが、私たち家族への複雑な思いを隠そうとはしなかった。
娘の私が、親子ほど年の離れた男性と旅していることも、彼の目には良からぬものとして映っただろう。
「先生、私は誰に謝ればいいのでしょう?」
川を眺めてゆっくり歩きながら、先生に聞いた。
「謝る?すぐに謝ろうとするのは鴨下さんの悪いくせですね」
先生は少し渋い顔をした。
「生きているだけで罪なものです。人間は」
まあ、そうかもしれない。
「先生も誰かに憎まれたことはあるんですか?」
「脇腹を刺されたことがあります」
「ええっ!? いつの話ですか?」
「若い頃と、比較的最近と、左右1回ずつ」
「!?」
「車を燃やされたこともあります。別の人を乗せたのが気に入らないとかで」
もはや私は声も出ない。持ち前の情熱の量が違いすぎる。
「しかし相手を恨んだことはありません。ただの一度も」
鳴滝先生はさらりと言ってのけた。
「鴨下さんのお母さんが塩見さんを訪ねるのは自然なことです。塩見さんがそれを拒むのもまた、悪くありません。世の中、やってはいけないことなんて、実はそんなにないのですよ」
「先生って優しいのか、正しいのか、わからなくなってきました」
「よく言われます。そして憎まれます」
しばらく無言で歩いた。
ド派手なレンタル着物に身を包んだ観光客の一群が、賑やかに通りを歩いていく。
路上では地元の高校生が、即興の拙いラップで戦っている。
とても格好いいとは言えない。でも、それだって悪くないのかもしれない。
母を見習ってしっかりした人になろうと思って生きてきた。その母は今どこでどうしているのか。しっかり者の母って一体誰だったのだろう。
私はスマホを取り出し、最近いちばんやりたかったことをやった。
「ママ、会いたいからそろそろ帰ってきてよ。私も圭もモナカもゴマもみんな待ってるよ」
父のコメントに続けた。
薄雲の奥で、冬の日が傾き始めていた。

鳴滝先生の運転で東京に帰ってきた。車が燃やされないことを祈ろう。
家では仏頂面の弟が待っていた。
「なんかこれ届いてたよ」
と、小さな包みを渡された。
割れ物注意のシールが貼られている。差出人の欄に「海野秀実」とある。海野くんからの音信なんて、2年前に別れて以来初めてのことだ。
弟の前で包み紙を解くのは気がひけるので、自分の部屋に入った。
蜂蜜だった。
瓶のラベルには筆文字で「蓮華草」とある。見覚えのある筆跡だった。
縦書きの便箋に書かれた手紙も同封されていた。
「お久しぶりです。元気ですか。先日、まさかという場所でお母さんに会いました。その時に約束した蜂蜜を送ります。味見してください。ラベルは僕が書きました。では」
ラベルも手紙もいい字だった。
海野くんの書く字は、間違いなく私の好きなもののひとつだった。書道サークルの展示で見た時、理屈抜きに好きだと思ったのだ。それは、今も変わっていないことを知った。変わらなくてもいいのだと思った。嬉しい気持ちだった。
ずっしりとした瓶の感触を手に感じながら、私はしばらくラベルを眺めていた。

日曜日、家で遅めの昼食をとっていた。車のトランクが閉まるような音が薄く聞こえた。
その直後、モナカとゴマが騒ぎ始めた。もつれ合うようにして、玄関に向かっていく。
ドアが開いた。
「ただいま」久しぶりに聞く母の声だった。
「おかえりなさーい」
ダイニングから呼びかけた。思ったより大きな声が出た。
玄関に行くと、少し髪の伸びた母が立っていた。
「ママ、元気だった?」
「元気よ。とっても楽しかったわ」
「よかった。で、どこ行ってたの?」
母と私は、顔を見合わせて笑った。
モナカが母の足元で「ウニャー」と甘えたような声を出した。
了
文/大澤慎吾 写真/吹田ちひろ









